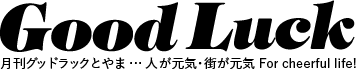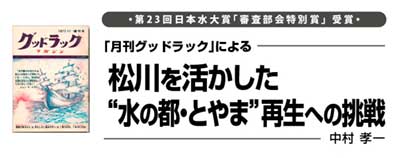富山売薬の礎を築いた5代藩主前田利幸〈としゆき〉公
きっかけを作った正甫〈まさとし〉公
全国的に知られる「越中富山の薬売り」のきっかけを作ったのは、ご存知のとおり、富山藩2代藩主の前田正甫公である。
一方、『富山のセールスマンシップ 薬売り成功の知恵』(遠藤和子著・サイマル出版会)によると、富山売薬産業の育ての親は、5代藩主の前田利幸公であり、藩政230年間の中で最も善政をしいた名君なのだという。
それでは、同書をベースに利幸公についてみていきたいが、その前に正甫公についておさらいしておこう。
正甫公は、人並みはずれて大柄で気が強く、領内の水練熟達者と神通川で泳ぎの技を競い合うなど意気軒昂であったが、天和元年(1681)、33歳ごろから身体に変調をきたしたという。正甫公は、ときどき襲う激痛発作を薬で抑えていたが、天和3年の発作は容易に治まらず、たまたま、近侍の日比野小兵衛〈ひびのこひょうえ〉が差し出した「延寿返魂丹〈えんじゅはんごんたん〉」を服用したところ、痛みはたちどころに治まった。小兵衛の話では長崎に出張した折り、腹痛で苦しみ、親しく交わっていた備前国医師、万代常閑(まんだいじょうかん)にもらった延寿反魂丹で治まったことから薬の製剤法を伝授してもらい、以来、常備薬にしているという。これを聞いた正甫公は、すぐに常閑を招き、御前調合をさせた。
元禄3年(1690)12月15日(現1月13日)、正甫公は、将軍綱吉に歳暮の挨拶と病気回復の報告をするため、江戸城大広間で謁見の順を待っていた。その時、部屋の外でざわめく気配がした。なにげなく座を立ち襖を開けると、中庭を隔てた帝鑑間〈ていかんのま〉(譜代大名の詰所)前の廊下を茶坊主たちがあわただしく行き来している。正甫が通りすがりの茶坊主に声をかけた。
「何事が起きたのか」
「陸奥国三春(福島県)当主、秋田信濃守(輝季〈てるすえ〉)様が差しこみ(胸や腹などの突然の激しい痛み)を起こされたのです」
輝季とは、天和元年、越後騒動による高田藩改易のとき公役で知り合い、同年齢で若くして襲封(諸侯が領地をうけつぐこと)したこともあり、互いに好感を抱き、以後、登城で顔を合わせるたびに親しく言葉を交わし合う仲だった。
正甫公が帝鑑間に駆けつけると、輝季が右手で腹部を押さえ、体をよじりながら苦しんでいる。額から脂汗がにじみ出ている。周りでは大名たちが慌てふためき、おろおろしている。正甫公は輝季に駆け寄り、すばやく腰の印籠から丸薬を取り出すと、白湯とともに口に含ませた。ほどなく輝季の顔に赤みがさし、静かに目を開けた。激痛が治まったらしい。
「あれほどの激痛が治まるとは…」
「なんとすばらしい霊薬!」
「薬は、死んだ魂も蘇るといわれる延寿返魂丹で…」と語る正甫公。
居合わせた大名たちは、この薬が富山藩では薬種屋の手で造られ、市場に出回っていることを聞くと、口々に頼んだ。
「ぜひともわが藩に売り広めてくださるまいか」
正甫公は、翌年(1691)5月、富山城に戻ると、薬種屋・松井屋源右衛門〈げんえもん〉に依頼藩の売薬回商を命じた。
産業として育てた利幸(としゆき)公
延享2年(1745)、利幸が17歳で藩主となったとき、藩財政は困窮の極みに達していた。利幸は領民たちの困窮生活を救済するため、お救米を与えたり、貸与米を配ったりした。一方、城下町中心の流通機構の整備に当たった。そして、財政再建にも思いをめぐらし、「鉱物資源に乏しく、山林面積にも恵まれぬ富山藩での他国市場を目当てとした産業の開発」として、売薬産業に着目した。利幸は、「反魂丹役金の取り立て停止」を実施。この触れに売薬商人たちは躍り上がって喜んだ。仕事に勢いがつき、売薬仕事に従事する者が増えた。一方、利幸は、参勤で江戸に出ると、売薬商人受け入れ工作に励んだ。登城すれば、諸大名の詰間を回った。また、江戸家老を諸藩の屋敷に派遣しては頼み込んだ。このようにして新しく許可を得た藩は、商人たちの働きも含めて32藩。振り売り行商圏も合わせると全国一円に広がった。販路は大きく躍進し、売薬に従事する商人の数は一挙に1000人を超えた。こうして、反魂丹売薬は富山藩独自の国産として定着したのだという。反魂丹役金は、文化2年(1805)に復活するまで53年間据え置かれた。
利幸は、宝暦12年(1762)9月4日、富山城で34歳の生涯を閉じた。その贈り名は、「霑慈院〈てんじいん〉」(うるおうばかりの慈悲を与えた意)であった。
◆参考リンク
「5代藩主前田利幸公と宝暦事件」(リンク)